
History
青野海運グループの軌跡

1894 明治27年
1921 大正10年
第一章 黎明期(明治)別子銅山の御用達商人に
-

明治27年に青野重松が創業
1894年に青野重松が創業。別子銅山への物資供給を始め、無機化学品の輸送やタンク輸送の先駆者として業界での地位を確立した。
-

元禄4年に別子銅山稼
1690年、坑夫・切上り長兵衛が別子山村で銅の露頭を発見し、住友家に知らせたことが別子銅山の誕生の契機に。1691年に稼働開始し、歓喜間符と名付けられた坑道が開発された。
-

静かな漁村だった新居浜
別子銅山開坑時、新居浜は静かな漁村だったが、住友の銅産業発展で一変。 粗銅輸送や生活物資の集積地となり、繁栄を見せた。青野海運の発祥地も、この賑わいの一翼を担っていた。
-

煙害防止が化学工業生む
別子銅山の製錬技術が西洋化され、銅の生産が拡大すると、新たな課題として煙害が浮上。住友は煙害防止のため硫酸や肥料を製造。青野海運は、これら製品の輸送を担い、化学工業の発展を支える重要な役割を果たしていった。
-

当初は資材納入が主力
別子銅山開坑時、新居浜は静かな漁村だったが、住友の銅産業発展で一変。 粗銅輸送や生活物資の集積地となり、繁栄を見せた。青野海運の発祥地も、この賑わいの一翼を担っていた。
-

2代目・市太郎も家業に従事
明治末期、四阪島移転により輸送が拡大し、青野回漕店も成長の機会を得た。長男・市太郎は、岩塩や醤油の輸送販売に尽力し、商才を磨いた。親子の努力で事業は徐々に軌道に乗り、発展を遂げた。
-

肥料製造所の製品輸送
四阪島での製錬開始後、住友は煙害対策として肥料生産を開始。1917年、青野回漕店が肥料の輸送を担当し、地道な努力で輸送量を拡大。1920年には契約が集約され、事業を一手に引き受けるようになった。
-

森実組と共同鉱石部設立
1917年、青野回漕店は森実組と共同で鉱石部を設立し、硫酸滓輸送を開始。住友の配慮で共同運航が進められ、青野回漕店は全国トップクラスの規模に成長。市太郎は金光教への信仰を深め、感謝と誠実さを経営に反映させた。
1922 大正11年
1936 昭和11年
第二章 始動期(大正)タンク船の開発に心血注ぐ
-

1、2回とも苦い経験味わう
関東大震災後、硫酸の需要が増加し、青野回漕店は日本初のタンク船輸送に挑むも失敗。試行錯誤しながら改良に取り組んだが、再挑戦も事故で沈没。しかし、住友の支援と挑戦の精神で、硫酸輸送に向けた新たな道を模索し続けた。
-

3回目のトライで成功
青野回漕店は3度目の挑戦でタンク船輸送に成功。光輝丸の運航により、日本初の大量硫酸輸送を実現し、住友からの信頼も厚くなる。市太郎の大胆な決断と住友の技術支援が功を奏し、その後も硫酸タンク船を増強し、輸送網を全国へ拡大。
-

3代目・青野重馬が入社
1934年、青野海運に市太郎の長男・重馬が入社し、三代目として経理や総務を担当。法学部出身の堅実な性格で祖父・重松の信頼を得た。重馬の入社により、市太郎は営業に専念し、社業をさらに拡大した。
-

第1号の社船・第5光輝丸建造
青野回漕店は初の新造船「第5光輝丸」を建造。最新鋭の機帆船として完成。しかし、その進水を見届けた創業者・重松は1ヵ月後に他界。裸一貫から41年間、家業を築き上げた重松は、厳格ながら情け深く、家族や人々に愛される存在だった。
-

第7・第8光輝丸を次々建造
1935年、重松の死後、市太郎が二代目として家業を継承。翌年、住友化学工業から長年の功績を評価され表彰されると、「第7光輝丸」「第8光輝丸」を建造。短期間で3隻の新造船を導入し、安定輸送と資金力を示し、経営を強化した。
-

新居浜港防波堤の捨て石工事
大正から昭和にかけて、青野回漕店は住友別子鉱山の要請で新居浜港の防波堤工事に参加。これを機に鉱山用の骨材納入も始め、業務を拡大。1937年、社名を青野運送店に変更し、船舶運輸のさらなる発展を図った。
-

市太郎が第1期市議会議員に当選
市太郎は、新居浜市が市制を施行した同年12月、市議会選挙に当選。消防団長や村会議員を経て、地域の合併促進に尽力。信仰心と海運業の経験を生かし、地域社会に貢献した。
1923 昭和12年
1944 昭和19年
第三章 激動期(戦前)太平洋戦争で苦難の道
-

第8光輝丸に徴用指令
1937年以降、戦時体制が強まり「第8光輝丸」が軍に徴用され、海運統制も厳格化。青野運送店は厳しい状況下でも新造船を建造し、住友の依頼で石炭や製品の輸送を継続。石油消費規制にも対応し、戦時体制に順応した。
-

昭和17年、青野組に改称
1942年、青野運送店は「青野組」に改称し、国家統制の強化に対応。同年6月、地元海運会社の統合で「新居浜海運株式会社」が設立され、青野組も参画。市太郎が常務取締役に就任し、戦時下の輸送統制や石油割り当て業務を担った。
-

『液体工業薬品槽船運輸』に参加
1942年、青野組は「液体工業薬品槽船運輸統制株式会社」に参加し、運航統制を強化。主に住友系の化学品輸送を担い、1943年からは住友共同火力の要請で石炭輸送も開始し、電力供給を支えた。
-

深刻だった機帆船事情
1943年、戦時統制の強化により青野組は「木船海運協会」と「愛媛機帆船運送」に関わり、厳しい燃料規制下でも運航を維持。また、新居浜港の港湾統合で「新居浜港運株式会社」に参加し、荷役や艀運送、代理店業務にも従事した。
-

陰から企業支えた重馬
青野組は貨物船、薬槽船、港湾運送の3本柱を経営の基盤とし、市太郎が外交、重馬が金庫番として内を支える体制で戦時中も継続。重馬は理論派として終戦まで陰から青野組を支えた。
1945 昭和20年
1954 昭和29年
第四章 復興期(戦後)住友企業の発展とともに
-

タンク船5隻で再出発
終戦後、青野組は老朽化したタンク船「光輝丸」5隻で再出発。戦時中の被害を免れた小型船が再建の基盤となった。1945年、市太郎の末弟・春歳と四男・節夫が入社し、それぞれ経理・総務、営業を担当し再建を支えた。
-

住友の硫酸工場も生産再開
終戦後、住友の再建は財閥解体で遅れたが、日新化学工業(現:住友化学)が硫安生産を再開。1946年、青野組は大阪出張所を再開し、住友との輸送業務を強化した。
-

海運軸に再建期し青野海運社
1947年、青野組は「青野海運社」に改称し、住友以外の南海化学工業との取引も開始。1948年には大分出張所を開設し、大阪や大分方面への輸送を強化。同年、新居浜海運株式会社を設立し、市太郎が常務取締役に就任。
-

新居浜港の開港で活躍
青野海運社は新居浜港の築港工事に貢献し、開港記念日に感謝状を受けた。また、重馬は新居浜市議会副議長に就任し、地域振興を目指して新居浜港の開港にも尽力。信仰を基にした地域貢献を続け、市議を6期24年務めた。
-

いち早く船腹拡大に努める
戦後の自主運航時代に向けて、青野海運社は船腹拡大に努め、資材不足の中で中古船を購入。1948年に『大宝丸』、1949年に『海福丸』を加え、運航体制を強化した。
-
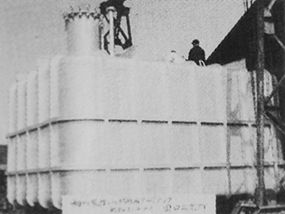
硝酸のタンク船輸送開始
朝鮮戦争を機に薬品タンク船輸送を強化し、青野海運社は硝酸輸送を開始、独自にアルミタンクを開発。また、別府化学など非住友系列の取引も拡大し、新居浜港での港湾業務や廃酸輸送にも取り組み、事業を多角化していった。
-

発煙混酸用に第21光輝丸建造
1953年、青野海運社は日本油脂の武豊工場向け発煙混酸輸送のため、『第21光輝丸』を新造。市太郎も同行し、順調な航海を見届けた。翌年にはホルマリンやメタノールの輸送も開始し、タンクの製作に注力。輸送力向上に期待が高まった。
1955 昭和30年
1963 昭和38年
第五章
成長期(昭和30年代)
経済成長の波に乗って
-

青野海運株式会社に改組
1955年7月、青野海運社は法人化し「青野海運株式会社」となり、タンク船、艀輸送、雑貨、骨材納入を主軸に拡大。若手社員の育成や労組交渉を進め、強固な経営基盤を築いた。
-

晒液、塩酸など新貨物増加
1956年、青野海運株式会社は住友化学の要請で晒液と塩酸の輸送を開始。ゴムライニングタンクを開発し問題を解決。また、桜島出張所を開設し、子会社の丸重海運を設立し輸送力を強化した。
-

液体アンモニアの輸送始める
1957年、青野海運は住友化学の依頼で液体アンモニア輸送を開始し、韓国・釜山にも展開。船腹を拡充し、希硝酸や晒液など輸送品目を拡大。1958年、市太郎は地域振興の功績で胸像が贈られ、四国地区海運組合連合会会長に就任。
-

貨物船に小型鋼船ブーム
1955年代、小型貨物船の鋼船化が進んだが、タンク船では遅れていた。硫酸や硝酸が鉄を溶かすため、木船が適していると信じられ、鋼船が溶けるという迷信も広まっていた。
-

初の鋼船・第1金光丸建造
1960年、青野海運は初の鋼船「第1金光丸」(139G/T)を建造し、硫酸輸送に使用。並行して「第1別府丸」「第2別府丸」など木船も建造し、工業薬品の輸送に活躍した。
-

鉄筋コンクリートの社宅竣工
1960年、青野海運は鉄筋コンクリートの社員住宅を建設。「庄内アパート」として完成し、福利厚生を強化。続いて寮「双葉荘」も設置し、社員の交流を深めた。
-

36年、一挙に3隻の鋼船進水
住友金属鉱山株式会社、住友化学工業株式会社の出荷量増大 昭和35年、政府(池田首相)が国民所得倍増計画を決定。日本の高度成長がスタートした。それは積極的で前向きな商売をする市太郎の感覚にぴったり合致した。市太郎はさらに一 […]
-

第8、第11金光丸と鋼製艀建造
1962年、青野海運は「第8金光丸」「第11金光丸」などタンク船と鋼製艀を建造し、壬生川~大阪間の定期航路を開設。内航二法が制定され、業界の組織化とオペレータ体制が進展。市太郎は内航海運組合の監事に就任した。
1964 昭和39年
1972 昭和47年
第六章
充実期(昭和40年代)
社訓十則に企業姿勢
-

貨物船不況を横目に順調
1965年代、日本経済の下降局面や内航業界の船腹過剰問題に対応する中、青野海運は無機化学輸送で順調に業績を伸ばした。1966年に内航総連合会が発足し、スクラップ・アンド・ビルドの建造制度が導入され、内航船業界の再編が進んだ。
-

のれんに対する大きな信用
昭和40年代初期の青野海運株式会社の売り上げの推移をみると、40年度が約3億5,400万円、41年度が約4億1,600万円、42年度が約5億9,200万円となり、1年間で6,000万円から1億円の伸びを見せた。これはひと […]
-

経営再建に重馬が大なた
順風満帆で業績を伸ばしてきた青野海運株式会社であったが好事魔多し。昭和40年から41年かけて創業以来、初の大ピンチを迎えた。経理担当者の不祥事で資金繰りが苦しくなったのである。慎重派の重馬が本社を見ていたが、部下を全 […]
-

43年に市太郎会長、重馬社長
1968年、青野市太郎が会長、青野重馬が社長に就任し、青野海運は三代目の時代へ。慎重派の重馬は市議会議長も務め、誠実さで周囲に信頼された。1969年には四代目社長となる青野正が入社し、現場で3年間の研修を経て営業に転じた。
-

硫酸専用タンカー・第58金光丸
1969年、青野海運は同和鉱業と取引を開始し、同社の岡山硫酸センターと住友化学新居浜製造所間の輸送を担当。初の硫酸専用タンカー『第58金光丸』を建造し、輸送効率が向上した。
-

44年に本社ビルが竣工
昭和44年には本社ビルを建設した。その前年には従業員用社宅の3棟目を完成(43年3月)し、社員の福利厚生施設を整備したばかりで、地元では青野海運株式会社の積極的な設備投資に目を見張った。本社社屋は新居浜市新田町1丁目12 […]
-

社訓と社訓十則を制定
昭和46年はドルショックに続き、変動相場制移行(8月)で経済が大きく揺れた。内航は長引く不況の中で貨物船の第2次共同係船案も検討されていた(47年3月実施)。こうした変動に対応するため、青野海運株式会社では組織強化を図っ […]
-

業績は順調に推移
安全・海洋汚染防止に留意 田中角栄通産相が「日本列島改造論」を発表したのは昭和47年6月であった(翌7月に田中角栄内閣成立)。これを引き金にして金融緩和と列島改造ブームにより、日本経済は高度成長のピークへと向かっていった […]
1973 昭和48年
1983 昭和58年
第七章
転換期 (昭和50年代)
オイルショックを乗り越えて
-

第1次オイルショック発生
別子銅山の閉山で青野海運は象徴的な存在を失ったが、同年の第1次オイルショックで燃料不足に直面。それに対しゼネラル石油との取引に集約し、輸送に支障なく対応し業績を拡大。さらに燐酸液の輸送が業務に加わり、輸送量も増加した。
-

難産だった第62金光丸
青野海運は倒産寸前の造船所から建造中の硫酸専用船『第62金光丸』を引き取り、完成まで自社で対応。重馬社長の適切な指示と法律知識により、エンジン設置や艤装を完了し、無事就航。これを機に、造船時の安全対策を強化した。
-

内航運送業1号業者へ昇格
運航船腹の増加に伴い、48年1月には内航運送業1号業者へ昇格(許可番号178)した。1号昇格の資格は、鋼船の運航船腹「5,000トン」が基準であった。 199G/Tの小型船が多い薬品タンク船業者が1号業者の資格を取るのは […]
-

育っていく後継者たち
1974年、不況下でも青野海運は新たな輸送業務を開拓。重馬の息子たちも後継者として成長し、特に日美は営業で経験を積んだ。重馬は地域・業界活動に貢献し、社歌制定で団結強化を図った。
-

市太郎88歳の大往生(勲四等瑞宝章受章)
昭和51年4月30日、事実上の創業者ともいえる市太郎が死去した。満88歳の大往生であった。前年に米寿を迎えて「赤い頭巾でお祝いしました。出席した孫や社員さんにもお小遣いを手渡すなど元気でした」(青野田鶴子)。1ヵ月ほどの […]
-

2代目、丸重海運株式会社を設立
四阪島製錬所が72年間の銅製錬に終止符を打ち、住友化学は愛媛製造所を発足。同年12月、青野海運は液体アンモニア船保有のため、丸重海運を復活設立し、初代社長に青野節夫が就任。
-

古希を迎えた青野重馬
1977年、重馬は古希を迎え、新居浜商工会議所会頭に就任。商工会議所会館の建設を主導し、地域経済振興に尽力し、紺綬褒賞と勲五等双光旭日章を受章。同年、新造船「第75金光丸」が竣工し、新規輸送事業を拡充した。
-

第2次オイルショック勃発
第2次オイルショックで燃料価格が高騰し、青野海運は燃料油対策協議会を設立し対応を強化したが、内航業界全体が不況に陥り、青野海運も5年間業績停滞を余儀なくされた。それでも一致団結して困難に立ち向かった。
-

管理部門を分離、丸重興産株式会社設立
青野海運は経営効率化を進めるため、営業所の移転や役員体制の刷新を行い、57年には管理部門を分離して丸重興産株式会社を設立。不動産や船舶管理を担当させた。営業努力も続け、住友化学工業などとの輸送業務を拡大した。
1984 昭和59年
1993 平成5年
第八章
飛躍期(昭和平成年代)
21世紀へ向け意識改革
-

バトンタッチへの準備
昭和58年3月、青野正が副社長に、青野日美が常務取締役に昇格した。重馬の次代へのバトンタッチの準備だった。正を社長見習いとし、役員陣を若返らせ社内を活性化していこうとの意図であった。重馬が市太郎から社長の座を引き継いだの […]
-

4代目の幕開け、正社長就任
1984年、青野正が社長に就任し、4代目の時代が始まった。正は人材確保を重視し、Uターン組や新卒者の採用を強化。現場勤務から育てる方針を取り、社員と船員の両方で企業の基盤強化を図った。
-
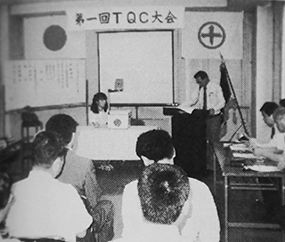
中期経営計画を策定
正は社長就任と同時に、59年度を初年度とする青野海運株式会社の中期経営計画を策定した。当時、正の右腕だった日野邦雄(当時営業部長)はその背景についてこう説明している「素材型産業からハイテク企業への生産の移行は、物流構造を […]
-

積極的な船腹拡充
正社長の積極策は61年から始まった。まずリプレースからで35年から41年にかけて大量に建造した船を次々と代替建造していった。不況下でも思い切った投資が出来たのは、先代の重馬の堅実経営のおかげだった。青野海運株式会社は創業 […]
-

四国商興(エースマリン)傘下に
ケミカル進出への足固め さらに平成元年には丸亀に本社を置く四国商興を買収し、青野海運グループの傘下に収めた。四国商興は昭和30年12月に四国化成工業株式会社丸亀工場の二硫化炭素の海上輸送を目的に設立された会社で当時、次の […]
-

倉庫『アトラス』を建設
1990年、青野海運グループは新居浜東港に「アトラス」倉庫を建設し、営業を開始。多角経営で成長したが、バブル崩壊で内航業界は再び不況に。正社長は「企業経営五戒」を策定し、企業の本業徹底と社会貢献、環境配慮を掲げた。
-

総合物流業者への脱皮目指す
青野海運は2000年に売上100億円を目指し、総合物流業者への脱皮を計画。無機薬品輸送を基盤に倉庫や自動車部門の拡大、ケミカル・油タンカーの強化、人材育成が重要課題。また、グループ各社の成長と新規事業開拓にも注力した。
-

惜しまれた重馬会長の死去
重馬は正に社長を譲って6年後の平成5年2月9日、死去した。前日までいつものように出社し、書類に目を通し、その夜突然亡くなった。満84歳。同日、勲四等瑞宝章に叙せられた。 重馬は市太郎以上に公職が多かった。新居浜市会議員( […]
1994 平成6年
2003 平成15年
第九章 拡張期(平成中期)創業100年を迎えて
-

創業100周年記念事業の展開
平成6年(1994)は、青野海運株式会社にとって大きな節目の年であった。 青野重松が、明治27年(1894)に新居浜で青野回漕店を創業して、100周年を迎えたのである。 青野正社長は、創業100年の意義を次のように語った […]
-

イヨテクニカルの傘下入りとサイバーとしての発展
「イヨテクニカルを、Ⅿ&Aで傘下におさめませんか?」 この話を持ちかけてきたのは、伊予銀行であった。「同社は、生産設備の自動化や省力化、それに伴う計測制御など、電気・電子の分野で幅広い技術を持っています」 イヨテクニカル […]
-

阪神・淡路大震災の発生
平成7年(1995)1月17日未明、明石海峡を震源とするマグニチュード7.3の阪神・淡路大震災が発生した。 神戸の市街地を中心に約25万棟の住宅が全半壊し、阪神高速道路の高架橋が横倒しに倒壊するなど、甚大な被害をもたらし […]
-

センコー株式会社との取引開始
平成8年(1996)8月、エースマリンは、初の高温液体船として、1,000トン積の「扇栄丸」を新造した。依頼主は、オペレータのセンコー株式会社で、C重油の代わりに燃料として使用するためのアスファルトを、堺から旭化成の水島 […]
-

所属船舶が最大数となる
青野海運の創業100年から110年にかけて――平成6年(1994)から16年(2004)までは、ちょうど「失われた20年」の真ん中で、バブル崩壊を契機としてわが国が長期構造不況に陥っていた時期である。長引く不況を反映して […]
-

渡邊運輸の傘下入りと陸送・倉庫部門のアトラス統合
渡邊運輸株式会社の渡邊秀雄社長が、青野正社長に事業譲渡を持ちかけてきた。 青野正社長と渡邊秀雄社長とは、住友化学の輸送業者として顔馴染みであった。渡邊運輸は、事業承継問題を抱えていて、この話を持ちかけてきたのである。 渡 […]
-

グローバルスタンダードへの取り組み
新世紀の幕開けとなる平成13年(2001)は、青野海運にとって、グルーバルスタンダードへの取り組みを本格的に開始した年である。 ISOの認証の取得 最初に取得すべきは、ISO9002の認証であった。 ISOとは、スイスの […]
-

後継者・青野力の入社と青野正社長の地域貢献
平成13年(2001)3月、青野正社長の長男・青野力が青野海運に入社した。 青野力は、入社と同時に飯野海運株式会社に出向を命じられた。飯野海運では、3年間、船舶管理の仕事を担当して、海運の知識を幅広く吸収した。青野力は、 […]
2004 平成15年
2024 令和6年
第十章 展開期(平成後期~令和)外航海運に本格進出
-

青野力の経営参画
青野力は、3年間の飯野海運の出向を終えると、平成16年(2004)に青野海運に復帰した。入れ替わりのように、それまで青野海運に勤めていた青野光年取締役と加藤嘉彦専務取締役が退任した。 青野海運に復帰した青野力は、東京支店 […]
-

リーマン・ショック
平成20年(2008)は、1月に原油先物相場が急騰してニユーヨークで1バレル100ドルを記録し、東京証券株式所の日経平均株価が535円35銭値下げするなど、波乱含みの幕開けであった。 9月、世界的な金融危機が襲い、わが国 […]
-

営業拠点を東京支店に集約
青野海運の主要荷主である住友金属鉱山や住友化学では、インターネットの活用により全国の工場や支店間とのコミュニケーションが容易になったことから、決裁権を東京本社に集中させて業務の効率化を図った。 これまで青野海運は、荷主の […]
-

「円高」不況
経済紙の紙面には、連日のように「円高」の文字が載った。 「リーマン・ショック」が起きた平成20年(2008)、為替相場において円は「安全な資産」と評価されていた。わが国が、巨額の経常黒字を続けたことで、世界最大の対外債権 […]
-

東日本大震災の発生
日本を襲う激震と波濤は、「円高」だけではなかった。 平成23年(2011)3月11日14時46分18秒、東日本大震災が発生して、太平洋沿岸部を巨大な津波が襲った。 三陸沖を震源とするこの地震の規模は、我が国観測史上最大と […]
-

外航への本格挑戦
外航海運では、平成9年(1997)に青野正社長が建造を命じた「リリウム ガス」を嚆矢として、21年(2009)に購入したプロダクトタンカー「TORM AMAZON(トーム アマゾン)」の運航で、貴重な経験を積んだ。 「ト […]
-

創業120周年と青野正会長・青野力社長の新体制
平成26年(2014)、青野海運は、創業120周年を迎えた。 青野海運では、「社会に奉仕・還元する」をコンセプトに据えて、次のとおり創業120周年記念事業を展開した。 6月1日、青野海運グループのホームページをリニューア […]
-

海運不況の嵐
外航船舶は、造船所へ発注してから竣工に至るまで数年を要する上、解撤(スクラップ)までの期間が長い。このため、外航海運は需給ギャップが生じやすい産業である。 平成22年(2010)から24年(2012)にかけて、「リーマン […]
-

青野正会長の受賞の栄
青野正会長は、本業の海運業はもとより、地域の産業経済、スポーツ、教育、科学及び文化の振興など、幅広く力を尽くした。 こうした青野正会長の多岐にわたる功績が認められて、平成6年(1994)に紺綬褒章と第六管区海上保安部長よ […]
-

安全管理と新型コロナウイルス対策
外航海運は、エマージングリスク(地政学的リスク・気候変動リスク)はもとより、業務遂行上のリスク(運航・操業リスク、災害・疾病リスク、人権にかかわるリスク、サイバーセキュリティリスク、為替・金利・燃料油変動リスク)など、様 […]
-

ウクライナ戦争
ロシアのウクライナ侵攻は、青野海運に戦後最大の危機をもたらした。 令和4年(2022)の武力紛争勃発により、ウクライナのオデッサ、ユズニー、チョルノモルスクなどの港湾に出入りしていた貨物船100隻以上が、黒海に封じ込めら […]
-

夢は世界、日々は〝当たり前〟の積み重ね
五代目の青野力社長は、自らの考えとビジョンを積極的に語る経営者である。 「私の座右の銘は、『和合』です。和合には、みんな仲良く、親しんでという意味もありますが、もう一つ『調和』という意味もあると思います。無理をするとどこ […]
-

21世紀の航海
この30年間は、まさに「激動の時代」であった。 青野海運にとっては、外航海運に本格進出を果たすとともに、積極的に事業の多角化を図ることで、飛躍と成長と発展を遂げた時期であった。また一方では、続けざまに危機に見舞われた艱難 […]








