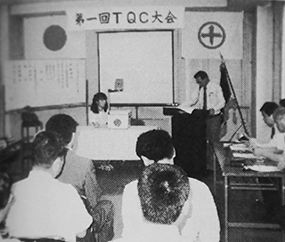中期経営計画を策定
正は社長就任と同時に、59年度を初年度とする青野海運株式会社の中期経営計画を策定した。
当時、正の右腕だった日野邦雄(当時営業部長)はその背景についてこう説明している
「素材型産業からハイテク企業への生産の移行は、物流構造を大きく変えつつあり、当社を取り巻く業務環境は極めて厳しい局面を迎えております。
このような構造の変化は、単に関係荷主業界にとどまらず、消費、地域経済、貿易等、経済の構造変化へと波及しております。」
全員参加のTQC運動推進
「当社の事業主体であります内航海運でも、物流の構造変化は、ケミカル製品類の輸入を中心としたターミナル基地の建設、石化産業の集約化、メーカー間における生産の委受託の促進、その他スワップ輸送の強化などにより内航船の船腹過剰が表面化し、内航海運における構造不況は深刻の度を増しております。
このような背景により、今後の物流業界においては、口先だけの「物流合理化」で片づけるわけにはいきません。
物流のニーズの変化に対応した物流システムの総合的な見直し、開発なくして企業競争に打ち勝つことが出来ない厳しい淘汰の時代に突入しました。
永年の歴史を持つ当社の海運事業も、目の前に押し寄せている構造の変化によって生ずる第1波はもちろん、第2波、第3波の大きな変革の波を乗り切るためには、今こそ全社員が総力を結集しなければなりません。その努力は当社が提唱している全員参加の品質管理活動(TQC活動)そのものです。この努力の結集が逆潮を乗り切る原動力となります。」
この頃、社内活性化策としてTQC活動やホウレンソウ運動を始めた。ホウレンソウとは、報告・連絡・相談の語呂合わせで、社内のコミュニケーションを良くしてチームプレーを向上させようとの狙いである。
これまで市太郎、重馬時代のトップダウンから、正の時代に入ってトップダウンばかりでなく、コミュニケーションを図りながらのボトムアップと、確実に社内ムードは変わりつつあった。
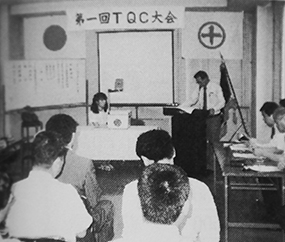
濃硝酸、安水輸送スタート
営業面でも活発化してきた。4月に日産化学工業株式会社の要請により住友化学工業株式会社愛媛工場から小野田向けの濃硝酸の輸送を行い、同月には愛媛工場から山口県光市の武田薬品工業株式会社への安水の新規輸送を開始した。使用船舶は『光洋丸』(船主・尾崎兼一)。さらに電力需要の増加に対応して、新居浜のコールセンターから住友共同電力株式会社向けの石炭輸送も行った。青野海運株式会社、森実運輸株式会社、浜栄港運株式会社3社の共同事業で、内外運輸の艀を用船した。9月には花王石鹸株式会社の要請を受け、住友化学工業株式会社愛媛工場菊本から川崎向けのアルキルベンゼンを輸送。近海タンカー株式会社から『第3にっける丸』を用船した。石炭輸送の増加に対応し同月『 1号』(船主・内外運輸)を百島造船所で建造、コールセンターと住友共同電力株式会社間のお手玉運航を行った。
1号』(船主・内外運輸)を百島造船所で建造、コールセンターと住友共同電力株式会社間のお手玉運航を行った。
正が社長に就任した59年は不況のまっただ中で出口の見えないトンネルの中に居た。翌60年後半からは円高不況がさらに覆いかぶさって来た。 61年には内航元請運賃が5~8%幅でダウンし、石油大手は専航船を2割ほど削減した。内航総連合会では58年度から「内航海運不況対策要綱」を策定し、61年度も同対策を発表、運輸省の指導のもとに過剰船腹の解消に取り組んだ。
青野海運株式会社も守りを固めた。社内では合理化・効率化を進めるため、TQC運動をさらに活発化した。 56年に運動を開始して以来、住友化学工業株式会社の考えに沿い、第1次3ヵ年計画では「事故防止」を目標に、第2次3ヵ年計画では「サービスアップ・コストダウン」を目標に掲げ取り組んできた。平成元年からの第3次3ヵ年計画は「高能率・高サービス」の物流、「無事故・無災害」の物流を目標とした。第2次の高サービスの中には事故防止が含まれており、一貫して無事故が基本となってきた。TQC事務局では、活動のベースになるのは「教育・研修活動」であり、それをもとに「小集団活動」及び「日常業務活動」と、これらが三位一体となって目標を達成していかなければならないと強調した。
社内体制をスリムな筋肉質にする一方で、正社長は積極策に打って出ることも考えていた。大胆にも「不況はむしろ飛躍のチャンス」と見ていた。暗くなりがちな社員に「燃えよ」と激励した。
59年11月の保有船腹
| 品 名 | 隻数 | 総トン数 | 積トン数 |
| 硫酸 | 9 | 2,424.25 | 3,960 |
| 液体アンモニア | 3 | 1,590.28 | 1,100 |
| 液体硫酸バンド | 1 | 198.00 | 450 |
| 硝酸 | 5 | 968.16 | 920 |
| 苛性ソーダ | 2 | 357.86 | 450 |
| メタノール | 2 | 263.78 | 500 |
| 廃酸 | 1 | 63.99 | 50 |
| 安水 | 1 | 109.94 | 50 |
| 24 | 5,976.26 | 7,480 |
全員一丸の燃える集団目指す
『本年も景気の減速で厳しい経営環境を覚悟しなければなりませんが、当社にとっては大変重要な1年であります。第1は、第1次中期計画の最終年度としてその成果が問われることであり、また、これを踏まえて新しい中期計画を策定しなければなりません。皆様の目標達成に対する一層の努力を期待します。第2は、昨年計画しましたIMO適合船が竣工、稼動を始め、スクラップ&ビルドによるIMO対応長期計画がスタートする年であります。
いずれも、当社にとりましては、社運を賭けるメインプランであることは言うまでもありません。日常、業務に生かしているTQCもさらに磨きをかけ、社内の3M(ムリ・ムダ・ムラ)を一掃し、全員一丸となって熱気溢れる「燃える集団」に変身し、この変革の時代を乗り切ってほしいと思います。
昨年から全社運動の一番手として取り組んできたホウレンソウ運動も、ますますきめ細かく継続していただくことで、社内チームワークを高め、お互いの仕事をより正確に推進できるものと思います。
また、改善提案についても自分の身の回りからムダを排除し仕事の効率を上げることから、さらに一歩進んで業務の新システムを開発し、業務の向上を計っていただきたいと願っております』(61年正月号の社内報)
ホウレンソウ運動も浸透
そしてこの頃、兄の正を支える右腕に成長していた日美常務(現・副社長)は、燃えるにはチームプレーと本音のぶつかり合いが大切だとフォローした。『サラリーマン社会というものは、とかく 『なあなあ』の世界である。矛盾とわかっていても、相手にそれを口に出して言うことは、はばかれる。特に、それを上司に言うのは至難の業ということになるだろう。その結果、上司に耳ざわりのよい、おいしい話しか耳に入って来なくなる。当然、上司の判断は甘くなり、進路を誤ることになる。それはもう企業の存在さえ危うくさせることにもつながるのである。
部下が上司に直言するのは難しいが、一方では上司も部下の直言に耳を貸す雅量を持つというのは意外に難しいものである。
まさに、言うは難し、行うはさらに難しである。しかし、上司と部下の間で本音で話し合えなければ、その企業が衰退するのは間違いのないことです。わが社における実態はどうであろうか、いま一度考えてみる必要があると思うのです。
わが社も「報・連・相」運動やQCサークル活動を通して燃える集団づくりを目指しているわけですが、もう一度原点に立ち帰った本音の行動を期待しています。そのためには、何事にも、勇気をもって決断し、実行し、常にチャレンジする精神を培い、明日の競争に打ち勝つ体質を身につけることです。しかも、上司も部下も本音で語ることができ、叱り、叱られて成長する「燃える集団づくり」を目指していきたい』(同)
会社設立30周年と会長の喜寿と健康を歓ぶ会 (昭和60年7月15日)