夢は世界、日々は〝当たり前〟の積み重ね
五代目の青野力社長は、自らの考えとビジョンを積極的に語る経営者である。
「私の座右の銘は、『和合』です。和合には、みんな仲良く、親しんでという意味もありますが、もう一つ『調和』という意味もあると思います。無理をするとどこかに歪みが出てくる。それはいけない。調和が大切です」
「和合」の後者の意味「調和」とは、言葉を換えれば「均衡」であり、「均整」であり、「バランス」であり、「ハーモニー」であり、「兼ね合い」ということであろう。
これが、人と船の双方に目配りをする青野力社長の経営の要諦である。
「船は、お客様の大事な荷物を運んでいる。このことを一瞬たりとも忘れてはなりません。船舶は、人類を支える『公器』で、輸送能力でいえば物流で最も重要な輸送機関です。影響が大きいがゆえに、一見理不尽とも思える規制が容赦なく降りかかるのだと理解しています。課題山積で辛いことも多いのですが、大変にやりがいのある仕事で、私は海運ビジネスが本当に好きです」
青野力社長は、青野重松・青野市太郎・青野重馬・青野正と受け継がれてきた住友精神「公」「自利利他」の体現者でもある。
青野力社長は、祖業を守りながら、外航へ本格進出を果たした。
「内航と外航の両方に取り組むメリットの一つに、円とドルの両方の収入があることです。外航はドル支払が大半なので、ドル支払があれば為替の影響を受けません。さらに足元は円安なので、為替差益のメリットがあります。経営者の立場では、外航船主となることで、色々なリスクの取り方や乗り越え方が分かるようになります。市況や為替だけでなく、戦争や海賊などの外航特有のリスクもあります。情報収集してこの先何が起こるか、どういう決断をしなければならないかなど、自分でシナリオを想定し、判断するには視野の広さが求められます」
「内航を止めて、外航に行く船主さんが多いですが、当社は、特殊タンク船による硫酸やアンモニアなどの危険物輸送を、オペレータとして輸送する責任があります。厳しい事業環境が予想されますが、祖業の内航事業を大切にし、成長の道を模索したいと思っています。
外航は、今後とも輸送需要は堅調に伸びることが見込まれているので、『内航と外航のハイブリッド経営』に取り組み、将来的には、外航でもオーナーオペレータを目指します」
青野力社長は、「内航と外航のハイブリッド経営」という概念を打ち出した。

省エネルギー船「光令丸」
「GHG(温室効果ガス)排出削減は、輸送業界にとって大きな課題です。当社は、以前から減速運行や省エネ船への投資に取り組んでいます。令和元年(2019)に竣工した『光令丸』は、優れた環境性能を持つ船として、国交省の内航船省エネルギー格付制度で、最高評価の星五つを得ています。
今後、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、重油から水素やアンモニアなどへの燃料転換の研究が進められていますが、これらは大型船向けの技術で、内航船への適用は相当厳しいと思います。
解決策の一つは、電気エネルギーだと見ています。輸送需要も含めた既存の条件が続くことを前提に、どういう船で、どのように電力を確保するかなど、二代目の市太郎が荷主さんと一緒にタンクを開発したように、これから荷主さんや行政などと連携して、チャレンジをしていきたいと思います」
青野力社長が語る「光令丸」は、令和元年(2019)に竣工した優秀船である。
「光令丸」は、499総トンの液体化学薬品ばら積み船で、翌2年5月に国土交通省の内航船省エネルギー格付制度で、最高評価の五つ星を獲得した。
この船の特色は、次のとおりである。
一 バルバスバウ(球状船首)を含めた省エネ船型を採用することにより、造波抵抗をより少なくし、燃費低減を図った。
二 省エネ主機関に減速機と大直径プロペラを組み合わせることで、燃費低減を図った。また、省エネ舵と組み合わせることで、大幅な省エネ効果になった。
三 航海支援システムを導入することにより、到着地までの最新気象・海象情報を収集し、航海時間の短縮や燃料消費量の削減を図った。
四 各船員の居住環境の向上を図り、防熱、防音にも配慮した。また、照明、航海灯などはLED照明を採用して、環境にやさしく維持管理が大幅に軽減できた。
「光令丸」のCO2削減効果の検証について、竣工時には、国土交通省基準値と海上試運転データ比較で26.09%の改善率であった。約1年後の実証結果は、当社船(2007年建造)との実船比較で20.8%の改善率であった。
令和4年(2022)、こうした省エネやCO2削減などの環境保全の積極的な取り組みが評価されて、青野海運は、国土交通大臣より交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰を受賞した。

SDGs経営方針
令和2年(2020)、青野海運グループは、「SDGs経営方針」を打ち出した。
青野正会長は、「社訓」とSDGsとの繋がりを、社員に諄々と説いた。
「先代の青野重馬、先々代の青野市太郎から受け継いできた『社訓』ですが、『神恩に報謝し』というのは、『やはり人間というのは、自分だけで生きているのではない、周りの環境に生かされていると考えて感謝しなさい』ということ。『社業に励み』というのは、『丸十のマークが象徴するように、社業は常に安定しており、皆で力を合わせて十分な力を発揮し、努力して頑張ろう』という意味。つまり、自分が生かされていることを理解して努力する、それによって助けられるという一つの流れです。その結果、『社会に奉仕する』。これは、『利益は、自分のために使うのではなく、還元しなさい、社会のために使いなさい』ということ。
社会への奉仕として顕著なものは、先代の青野重馬が、新居浜市に寄付してつくった青野記念奨学金です。その後、私が先代から会社を引き継いだとき、もっと子供たちに勉強して欲しいという思いから、奨学金を増額しました」
青野力社長は、「持続可能な経営」を、社員に熱い口調で語りかけた。
「平成27年(2015)に国連総会でSDGsが採択されたことにより、国連加盟国193カ国共通の目標ができました。
当社の主要なお客様である住友グループをはじめ、世界に名の通った上場企業がSDGsにコミットした経営を進めようとしています。我々もステークホルダーとして、一緒に進んでいかなければならない立ち位置にいるわけです。そのため、青野海運グループとしては、SDGsに取り組まないという選択肢はない。
一番申し上げたいのは、我々は既にSDGs理念の根幹である「持続可能(sustainable)な経営」を実践してきたということです。顧客及び地域と寄り添い125年以上事業継続できたことがそれを証明しています。
したがって、これまでの経営理念(社訓十則)からなるべく乖離しないように、現在の環境や人権問題など、新たなテーマが加わったSDGsの概念に近づけるにはどうしたら良いかということを考えて、『SDGs経営方針』をつくりました。
内航海運部門や陸運部門では、グリーン経営認証を取得して、『3R〔Reduce(リデユース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)〕により資源を大切に使おうという取り組みをしてきました。
今回のSDGsで、『気候変動に具体的な対策を』という目標ができたことを受け、温室効果ガスであるCO2排出量削減の目標を立てました。内航海運部門では、令和元年(2019)比で令和5年(2023)▲3%以上、令和7年(2025)▲5%以上と目標を立てています。
このため、船長・機関長には、各船舶のエンジン回転数を減らして、つまり減速して航海するようお願いしています。それにより、航海時間が増えて、船員の皆さんには負担をかけることになりますが、現在できる取り組みはそれしかありません。
今後は、燃料そのものを変えるというのが大きなポイントになります。あらゆる機関が、カーボンフリーエンジンの研究・開発に取り組んでいますが、我々もメーカーの方と情報交換をしながら、どの燃料が当社の船隊にフィットするか、検討を続けています。次世代燃料を使用する船舶へ投資することが、次のステップになります」
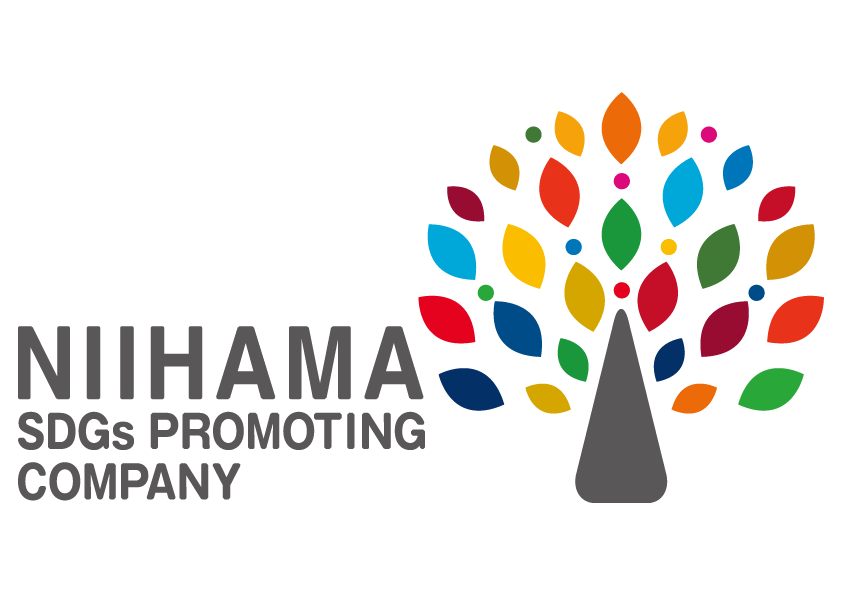
「健康経営優良法人」に認定
令和3年(2021)3月、青野海運は、「健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)」に認定された。
経済産業省の「健康経営優良法人」認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度である。
この認定により、青野海運は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」の取組みが優良であると認められた。
爾来、青野海運は、令和6年(2024)まで、4年連続で認定されている。
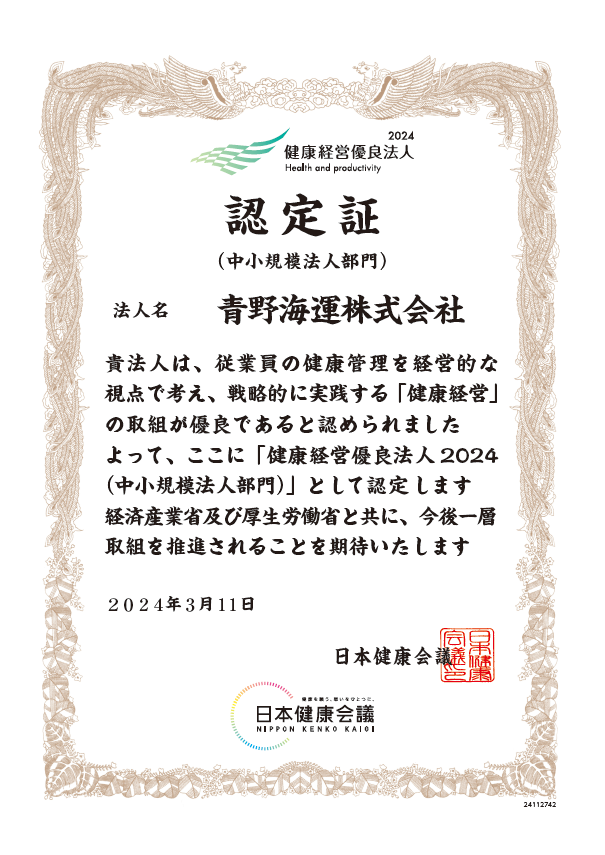
船隊の拡充強化
青野海運では、船隊の拡充強化に努めて、内航船15隻・外航船6隻を運航している。(令和7年2月現在)
【内航船】 15隻
平成19年(2007)3月 特殊タンク船「第三十光輝丸」(332G/T)竣工 タンクゴムライニング船
平成20年(2008)12月 油脂船「光皣丸」(498G/T)竣工 「第十ニッケル丸」のリプレース
平成21年(2009)8月 硫酸船「光駿丸」(498G/T)竣工 「第三大和丸」のリプレース
平成23年(2011)12月 特殊タンク船「圭昇丸」(185G/T)竣工
平成24年(2012)9月 多目的船「光絢丸」(330G/T)竣工 後に積荷を希硝酸専用に変更
平成26年(2014)5月 多目的船「光奉丸」(249G/T)竣工
平成27年(2015)5月 硫酸船「光泉丸」(199G/T)竣工
平成27年(2015)9月 多目的船「光翠丸」(377G/T)竣工
平成27年(2015)12月 硫酸船「光硫丸」(340G/T)竣工
平成30年(2018)6月 硫酸船「紀元丸」(198G/T)竣工
平成30年(2018)8月 硫酸船「光容丸」(199G/T)竣工 タンクテフロンライニング船
令和元年(2019)11月 多目的船「光令丸」(499G/T)竣工
令和4年(2022)9月 硫酸船「光和丸」(199G/T)竣工 荷主DOWAエコシステムの専用船として運航
令和5年(2023)1月 二硫化炭素船「光進丸」(320G/T)竣工
令和6年(2024)8月 液化ばら積船「光安丸」(749G/T)竣工
【外航船】 4隻
平成29年(2017)6月 液体化学薬品ばら積船「CHEMROUTE PEGASUS」(26,000DWT)買船
平成30年(2018)2月 ばら積貨物船「LESEDI QUEEN」(50,000DWT)竣工
令和元年(2019)10月 ばら積貨物船「CLARA INSIGNIA」(61,000DWT)竣工
令和6年(2024)10月 ばら積貨物船「GCL PRAIA MOLE」(82,000DWT)竣工
令和7年(2025)3月 ばら積貨物船(41,000DWT)竣工予定
令和9年(2027)1月 ばら積貨物船(64,000DWT)竣工予定
船隊の拡充強化について、青野海運の役職員は、次のように回想している。
「私は、平成10年(1998)に和泉海運有限会社の船長として『第十一光輝丸』を任されました。本船は濃硝酸運搬船で、カーゴタンクの材質はSN‐1という、国内で2隻しか存在しない貴重な船舶のうちの1隻です。当時は船主業に従事するためには特定の権利が必要でしたが、私にはその術がありませんでした。しかし、和泉海運有限会社を所有させていただき、青野海運グループの一員となる機会を得たことは、私にとって大変光栄な出来事でした。若かりし私にこのような大きなチャンスを与えて下さったこと、当時社長であった青野正会長の懐の深さは、今も忘れることができません」
「その後、船を降りた私は、平成18年(2006)に陸上社員として新たなスタートを切り、青野力社長のもとで数々の経験を積ませていただきました。特に省エネ内航船舶の建造、次世代船の研究に取り組むプロジェクトや、外航船舶を10隻所有するという壮大な挑戦では、青野力社長のチャレンジ精神と冷静な判断力、そしてチームの結束力と革新性を身近に感じ、会社の進化を間近で実感できていることに深く感謝しております」
(青野海運安全運航本部船舶管理部部長 汐口弘行)
「私は、平成20年(2008)8月の途中入社の身ながら、翌21年4月から東京支店に異動となり、はや15年が経ちました。異動当初より、ケミカル配船と東京営業を任されておりますが、その間2隻の専用船化を果たせました。ケミカル配船については、平成21年(2009)当時、499G/T船で『第三十二光輝丸』『第三十六光輝丸』を運航し、500t型で『第三光輝丸』『第五十三光輝丸』を汎用ケミカル船として運航していましたが、高船齢に伴う不具合も度々のことで、(10円禿が3つできる)大変な調整がありました。徐々に船齢に伴う除船を経て、令和4年(2022)6月をもって弊社ケミカル船はなくなってしまいました」
(青野海運営業本部内航営業部長 達川尚也)
「私の思い出に残るエピソードは、平成27年(2015)の1年間で3隻(『光泉丸』『光翠丸』『光硫丸』)を建造・竣工したこと。殊に『光翠丸』については、船名を社内公募で決定したこと、初めて進水式に荷主さんを招待せず、当社社員一同で進水式・祝賀会を開催したことです」
(青野海運シニアアドバイザー 竹野時史)
当たり前〟の実践
「祖業を守りつつ、青野海運グループを、世界に通用する会社にしたい」
青野力社長が想い描く夢は大きい。
この大きな夢を実現するため、社員たちに「〝当たり前〟の実践」を求めている。
「近年、世界を急速に繋いだのは『IT』ですが、実体経済を繋いでいるのは今も昔も『物流』です。令和2年(2020)から4年(2022)は、物流が経済に与える影響の大きさを人類が再認識した年であったともいえます。近年の物流業は運ぶことが〝当たり前〟で、他に付加価値が無ければサービス業として成立しないといわれてきましたが、コロナ禍で『運ぶことそのものが大きな価値になる』ことを、皆さんは色々な局面で目撃したのではないでしょうか。
しかし、物流業界の誰もがこの時期に利益を得た訳ではありません。むしろ想定外の利益を得たのはごく一部なのではないかと感じています。決定的な違いは、『必要とされるサービスを有事の際にも〝当たり前〟に提供できたかどうか』だったと思います。想定外の利益を得た方は、皆さん口をそろえて『たまたま儲けただけ』といいますが、この難しい経営環境でも、サービスを止めることなく〝当たり前〟に事業運営をしていた事実が、利益の本質です。その安定経営は、信頼を呼び、リピーターを呼んで、顧客との良好な相乗効果を生むことは想像に難くありません。
これは、物流に限らずあらゆる事業運営に通じ、さらには仕事だけでなく、個人の健康や自己実現にも通じる真理ではないかと強く思います。〝当たり前〟を〝当たり前〟に実践していくことの尊さを、再認識すべきというのが私の学びでした。
〝当たり前〟を実践していくには、『個』の力は勿論、『それを繋げて全体の力にしていくこと』が欠かせません。個が尊重される時代になったといわれますが、これは、ワーク・ライフのバランスをとろうとしているに過ぎず、人間は繋がって一つになることで力を発揮する生き物です。会社経営は、その典型的な例でしょう。他人と自分が違うのは当然で、会社での役割分担も異なる。しかし、それらが繋がってグループの力になっていることをもう一度自覚して、日々の〝当たり前〟を積み重ねられる組織をつくり上げましょう」
DXの推進
内航業界では、船員の確保・育成・定着が大きな課題となっている。
「これから年齢構成の30%以上を占める高齢船員の退職が本格的に進むなかで、既存船員の定着率を上げることが重要であることはいうまでもありません。特に若年層の定着率悪化と育成の遅れは、業界の致命傷となります」
青野力社長は、船員の定着率向上のための対策を講じた。
賃金アップはもとより、休暇サイクルの安定や船内居住環境の改善、船員の健康支援などの労働環境全体の整備に取り組み、30~40代の定着率向上には手応えを感じているものの、若年層の定着には課題を残す結果になっている。
「そこで私は、働きながら成長を実感することが船員の定着に繋がるという仮説を立てました。この仮説に基づく具体策として、組織的な評価制度を整備しようとしています。昇格に明確なハードルを設け、能力を正しく評価することで〝成長を実感〟させる仕組みです。陸上の世界では当たり前の仕組みですが、海上という職場の特殊性がそれを難しくしていました。
当社は、これをDXで解決します。令和6年(2004)から乗組員と陸上職員の双方向デジタルプラットフォームを導入し、試験運用を開始しました。また、船舶の次世代技術を積極的に取り入れ、船員に刺激を与えるといったことも意識して行っています。
評価制度に関しては、まず安全管理規定、ISM(安全管理システム)、環境保全、コンプライアンス等の社内の独自規定を全て見直して、統合した船員向け業務マニュアルを作成しました。やるべきことを明確化して、自身に不足しているスキルを理解して貰い、スキルアップしたら評価するという基本的なことから始めていきます。
デジタルプラットフォームにマニュアルと評価システムを反映し、リアルタイムにフィードバックを行いながら、評価結果を給料と昇格に反映させることを想定しています。そのなかでより高みを目指す人には、さらにモチベーションが上がるような仕掛けを取り入れていきます。いわば『海上職版reward system(報酬システム)』の構築を考えています」
青野力社長は、DXを推進するため、社内にDX推進課を設置した。ITスキルを持つ人材をヘッドハントしてリーダーに据え、デジタルプラットフォームの仕掛けをはじめとする種々の施策を展開している。
令和6年(2024)には、情報共有の効率化やコミュニケーションの活性化を図るため、株式会社スタメンが開発した社内アプリ「TUNAG(ツナグ)」を、青野海運グループ3社(青野海運・サイバー・アトラス)に導入した。
DXの推進について、青野海運の役職員は、次のような展望を描いている。
「経営資源として、ヒト・モノ・カネ・情報(データ)・組織力/文化が挙げられます。現在、Monday.comを活用して、配船から運航の情報が集約され始めています。これを業務改善(省力化)がメインの目的と捉える方がいるかもしれませんが、大きな狙いは、これまでExcelファイルに入力されて利用できなかったデータを、今後は利用・活用できるデータに変えること。工務課、代理店部、その他部門でも利用を拡大していきたいと考えています。業務を行うと必ずデータが生まれ、これら(Galileopt等に乗らないデータを含めて)は重要な資産となります。Monday.comは、これらのデータを関連付け、保存し、活用可能な状態にすることに優れており、実現すれば、会社の大きな力になります。他社よりも進んだ環境を構築できる可能性を感じています」
(青野海運経営管理本部総務・企画部DX推進課課長 平田竜祐)
青野力社長は、青野海運の将来像を次のように語る。
「最終的には、社員がモチベーションを高く保ち、自ら様々なことを考え、提案し、実践してくれるような会社を目指します」