硝酸のタンク船輸送開始
朝鮮特需で活気づいた産業界
昭和25年6月、朝鮮戦争が勃発、『朝鮮特需』を誘発し、日本の産業界を活気づかせた。機帆船は米軍に用船され、かなりの隻数が朝鮮に向かった。日本沿岸での輸送も活発化し、各地の船どころで係船されていた貨物機帆船が一気に動き出した。
艀で肥料類を阪神方面に輸送していた青野海運社は、一般貨物(ドライカーゴ)部門の輸送は新居浜海運株式会社に移行して、需要の回復とともに本来の主力業務である薬品タンク船の輸送に重点を移し始めていた。昭和25年には日新化学工業株式会社(現:住友化学工業株式会社)新居浜製造所の要請により、『宝力丸』を使用して硝酸のタンク船輸送を開始した。このため筒型横置式アルミニウムタンク2基を製作して設置した。

アルミニウムタンク独自開発
ちょうど硫酸のほか、塩酸、硝酸と品目も増え、輸送量も増加していた時期に当たっていた。薬品タンク船の最大のポイントはタンクの開発であった。戦前、硫酸タンク船就航までに市太郎が苦労したように塩酸や硝酸輪送でも関係者の苦労は並み大抵ではなかった。 中でも硝酸輸送は他社ではほとんど手掛けていなかった。硝酸のタンク船輸送でも青野海運社がわか国で初めてだった。そのため硝酸用のアルミニウムタンクを独自に開発しなければならなかった。工務担当は永易吉示(営業兼任)や田中猛らであった。
「住友化学工業株式会社から硝酸についての資料や材質の研究データを提供してもらい研究を重ねました。アルミニウムは純度が高いと硬度が低くなり、引っ張り強度が不足する。陸上のタンクで参考になるのは材質的な面だけで、海上でのピッチングやローリングに対応するため、問題が生ずるごとに、住友化学工業株式会社の技術陣と協議を重ね、アドバイスを受けながら解決していきました。」(田中猛)
陸上のタンクを製造する場合、法規で強度計算式が定められている。しかし、海上で使うアルミニウムタンクの仕様は皆無で監督官庁に問い合わせても明確な答えは返ってこなかった。仕方なく硫酸タンクを参考に底辺にかかる比重分の圧力、外圧の計算を鉄タンクの強度計算方式で便宜的に割り出し、タンクの高さを幾分縮めて設計した。しかし、前例がないので運輸省の許可がなかなかおりない。
最終的にはアルミニウムの肉厚などの強度計算をし、船舶のタンク規制に合わせた図面を提出してやっと承認された。タンクに使うアルミ材はアルミ純度が99.7%のものを用い、肉厚は12~16ミリ。テスト段階では硝酸の代わりに水を積んで何度も水圧試験を繰り返した。これでタンクの目途はついたが、もう一つ課題が残っていた。タンクを艙内にどのように固定するか、ということであった。鉄のベルトで固定すると鉄とアルミタンクとの接触面で腐食が起こる可能性があった。そこで海水をかぶらないようカバーをつくり、ペンキを塗って保護した。こうしてやっと硝酸のタンク船輸送が実現した。もっとも硝酸タンクは2年に一度ある船の定期検査まで使えればいい方だ、というぐらいの感触だった。
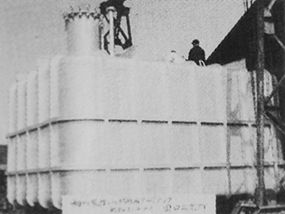
別府化学工業株式会社の製品輸送
住友以外の輸送では昭和25年に別府化学工業株式会社(現住友精化)の輸送を請負った。同社は、日新化学工業株式会社(現:住友化学工業株式会社)と株式会社多木製肥所の共同出資で設立された会社で前身は住友多木化学工業。昭和21年4月に社名を地名に因んで別府化学工業株式会社に変更した。株式会社多木製肥所はわが国で初めて人造肥料を手掛けた会社で明治18年、兵庫県加古郡別府村(現加古川市別府町)で骨粉を原料にした人造肥料の製造を始め、その後、大正、昭和を通じて過燐酸業界で重きをなした。昭和13年から硫酸工場が稼働し、新会社設立を経て戦後も硫安の販路拡大に力をそそいでいた。
青野海運社と同社との縁は従来から住友鉱業株式会社の四阪島製錬所から同社へ硫酸を輸送しており、その仕事振りを買われて別府化学工業株式会社もタンク船による輸送を依頼してきた。
アルミニウムタンク独自開発
ちょうど硫酸のほか、塩酸、硝酸と品目も増え、輸送量も増加していた時期に当たっていた。薬品タンク船の最大のポイントはタンクの開発であった。戦前、硫酸タンク船就航までに市太郎が苦労したように塩酸や硝酸輪送でも関係者の苦労は並み大抵ではなかった。 中でも硝酸輸送は他社ではほとんど手掛けていなかった。硝酸のタンク船輸送でも青野海運社がわか国で初めてだった。そのため硝酸用のアルミニウムタンクを独自に開発しなければならなかった。工務担当は永易吉示(営業兼任)や田中猛らであった。
「住友化学工業株式会社から硝酸についての資料や材質の研究データを提供してもらい研究を重ねました。アルミニウムは純度が高いと硬度が低くなり、引っ張り強度が不足する。陸上のタンクで参考になるのは材質的な面だけで、海上でのピッチングやローリングに対応するため、問題が生ずるごとに、住友化学工業株式会社の技術陣と協議を重ね、アドバイスを受けながら解決していきました。」(田中猛)
陸上のタンクを製造する場合、法規で強度計算式が定められている。しかし、海上で使うアルミニウムタンクの仕様は皆無で監督官庁に問い合わせても明確な答えは返ってこなかった。仕方なく硫酸タンクを参考に底辺にかかる比重分の圧力、外圧の計算を鉄タンクの強度計算方式で便宜的に割り出し、タンクの高さを幾分縮めて設計した。しかし、前例がないので運輸省の許可がなかなかおりない。
最終的にはアルミニウムの肉厚などの強度計算をし、船舶のタンク規制に合わせた図面を提出してやっと承認された。タンクに使うアルミ材はアルミ純度が99.7%のものを用い、肉厚は12~16ミリ。テスト段階では硝酸の代わりに水を積んで何度も水圧試験を繰り返した。これでタンクの目途はついたが、もう一つ課題が残っていた。タンクを艙内にどのように固定するか、ということであった。鉄のベルトで固定すると鉄とアルミタンクとの接触面で腐食が起こる可能性があった。そこで海水をかぶらないようカバーをつくり、ペンキを塗って保護した。こうしてやっと硝酸のタンク船輸送が実現した。もっとも硝酸タンクは2年に一度ある船の定期検査まで使えればいい方だ、というぐらいの感触だった。

(1月1日、金光教の教会前で)
共栄物産株式会社の経営肩代わり
東亜燃料の廃酸を新規輸送
昭和27年4月、日本は主権を回復し、産業界にも雪解けがやって来た。別子鉱業株式会社は6月2日、社名を住友金属鉱山株式会社に改称、社章もイゲタマークを復活した。日新化学工業株式会社も8月28日、社名を住友化学工業株式会社に戻した。
この頃大阪出張所では東亜燃料工業株式会社の廃酸を有田から和歌山(南海化学工業株式会社)へ運ぶ新規の仕事を手掛けた。キッカケは南海化学工業株式会社の紹介によるものだった。廃酸はなかなか難物だが、タンクに濃硫酸を2回ほど積むとタンクがきれいになり、無機タンク船には適した貨物だった。同業者取引でのニーズもあり、辰巳商会のアンダーとして廃酸専用船の『第6宝生丸』で三井金属鉱業株式会社の硫酸を運んだこともある。
